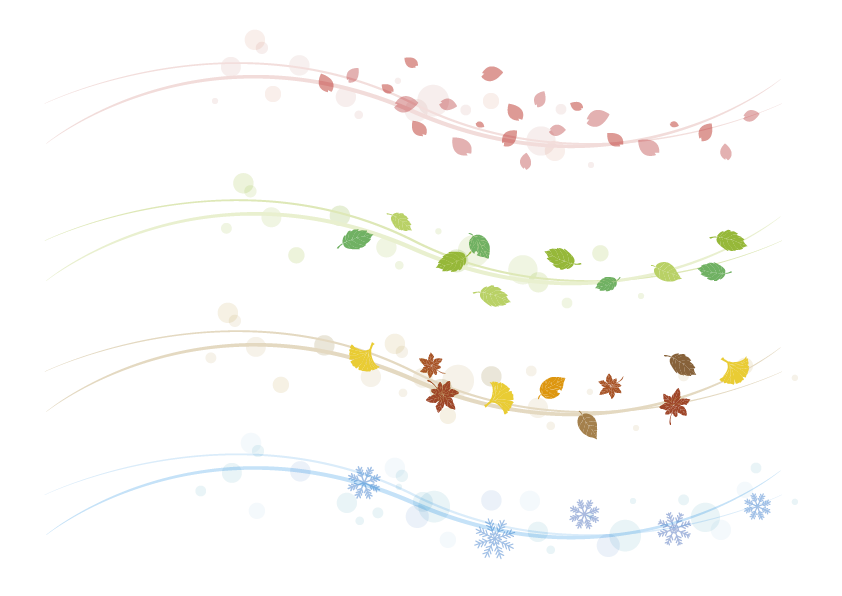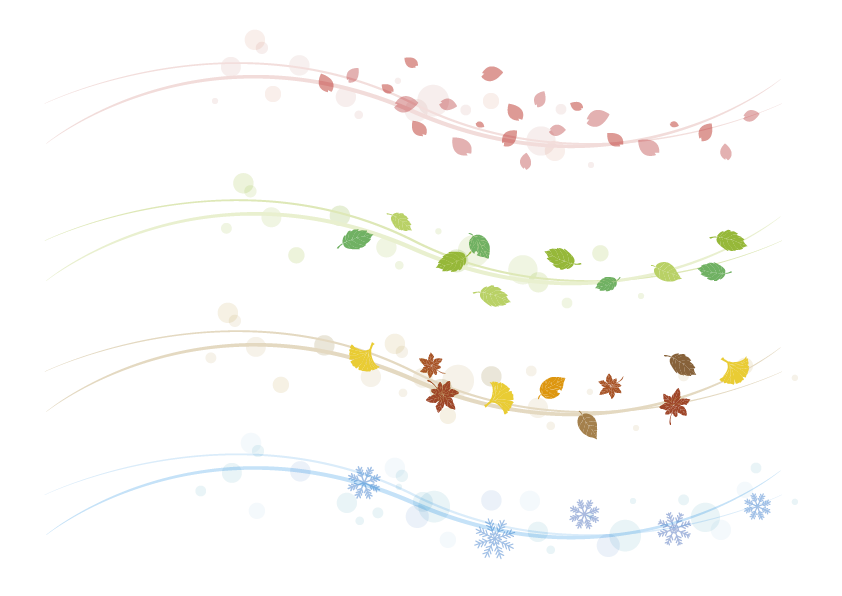
1年に1~2回は所属する学会の全国での総会に出席している。学会にでかける理由は人それぞれで、評議員や役員を務めている先生はそれらへの出席も必須だろう。私たち、ごく普通の一般病院の臨床医にとっての目的は、第一線、最新の知見に触れ、学術総会での発表なども通じてのキャリアアップ、医師としての自分を磨くということに集約される。その他にも、発表される症例報告などを通じて、日常診療で困っている症例や苦労していることなどの解決のヒントを探しに行くということもあるだろう。自身が行っている日常診療の妥当性を確認する場であるとも考えている。また、ほとんどの専門医のライセンスは学術総会への規定の回数の出席を義務づけているため、この目的もある。決して遊びに行くわけではないが、開催地によっては行ったことのない土地であることもままあり、旅行的楽しみももちろん見逃せない。
ところが最近の学会、あまりにも高度化、先鋭化し難解な内容になってきているような気がしてならない。正直「あまり面白くない」のである。私たち主にがんを扱う外科医にとって、最新の知見といえば、大規模な臨床試験の結果や、もはや理解困難な分子生物学的理論になってきつつあり、一般の臨床とはかなりかけはなれたものになっている。もっとも、抗がん剤などの創薬も以前とは全く異なり、”Biology first, not drug first”で、遺伝子レベルでの病態生理に基づいた開発であり、これらの理解が必要なのである。
また、EBMの定着に伴い、あらゆる疾患に診療ガイドラインが設定されている。おかげで全国どこでも最新の推奨される治療が受けられる均てん化がはかられ、学会でもこの内容が常に検証、更新されている。だが、反面、ガイドラインに載っていない治療や手技は認められづらい時代である。たとえば新しい手術術式や手技を考案し学会で発表したとしても、背景に膨大なデータに基づくエビデンスがなければその場限りで以後は誰にも相手にされないだろう。薬物治療などでも、がん診療の場合は特に臨床試験、メタアナリシスなどの確固たる証拠がない限り、決して認められることはない。日常診療でも全国に発信したいと思う症例や治療手技があってもメジャーな学会での発表はそう簡単なことではない。莫大なデータを有するハイボリュームセンターでない限り、一般病院の医師が全国学会で発表し勝負していくのはなかなか難しい世の中になってしまった感がある。
発表はおろか、聴講し理解することすら大変な労力を要する最近の学会参加ではあるが、気力が続く限りは細々とでも続けていこうと思っている。
|

 秋田市医師会報のあとがき「春夏秋冬」のご紹介です。
秋田市医師会報のあとがき「春夏秋冬」のご紹介です。